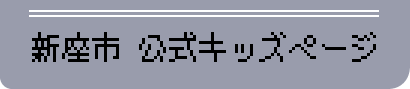旧石器時代(きゅうせっきじだい)から鎌倉時代(かまくらじだい)まで
新座市は、柳瀬川や黒目川の周りの低い土地と、それにはさまれた野火止台地からできています。
古くから住む場所としてだけでなく、交通や宿場としても重要な場所でした。
旧石器時代には、黒目川流域の市場坂遺跡や栗原遺跡などに、昔の人たちが生活していた跡が残っています。
市内には、旧石器時代から古墳時代まで、柳瀬川・黒目川の流域を中心に100か所もの遺跡があります。
弥生時代には、柳瀬川・黒目川流域の低地が水田となり、周辺の新開遺跡では複数の方形周溝墓(昔の有力者のお墓)が見つかりました。
古墳時代から奈良・平安へと時代が進むにつれ、河川の流域全体に家が広がり、村ができました。
奈良時代には、朝鮮半島の新羅から多くの人がやってきて、新羅郡になりました。
新羅郡はその後、新倉郡、さらに新座郡と名前を変えます。新座市の名前はこの新座郡がもとになっています。
その後、片山郷の出身である片山氏が、鎌倉時代から南北朝時代にかけて黒目川流域を中心に活躍しました。
一方、普光明寺や氷川神社を中心とする柳瀬川流域の大和田郷一帯にも文化が生まれ、市内は豊かな歴史的発展を始めました。
江戸時代(えどじだい)から現在(げんざい)まで
近世に入ると、江戸(東京)から近い場所であったことから、川越・高崎藩領をはじめ、片山七騎などが治めた旗本領や、天領、平林寺領がそれぞれ支配しました。
なかでも川越藩主松平伊豆守信綱による野火止用水の工事は有名です。
江戸時代には開発によってできた村などを含め、市内には15の村ができました。
これらの村々は幕末の変動を経て明治を迎えます。
明治8年(1875)4月、黒目川流域の片山の10の村は、合併して片山村となり、明治22年(1889)4月には、大和田町と野火止村ほか3つの村が、合併して大和田町になりました。
その後、昭和30年(1955)3月には、大和田町と片山村が合併して新座町が成立し、さらに昭和45年(1970)11月1日に新座市となりました。

▲新座市(にいざし)となった時(とき)の写真(しゃしん)
コラム1:野火止用水(のびとめようすい)はどうやってできたの?

むかしむかし、野火止用水には、野火止台地で暮らす人たちが飲む大切な飲み水が流れていました。
その水は、1655年に川越の藩主(えらい人)だった松平伊豆守信綱が、家臣(家来の人)の安松金右衛門に指示をして、
玉川上水(東京都小平市)の水を分けて野火止用水を作ったことによって、流れるようになりました。
今は、用水周辺には散歩できる道ができていて、自然を楽しみながらリラックスできる大切な道になっています。
コラム2:新座(にいざ)に伝わる民話(みんわ)
古くから地域に語り継がれてきたお話を「民話」と言うよ。
新座市に伝わる「にいざの民話」を、図書館のホームページから読んでみましょう。