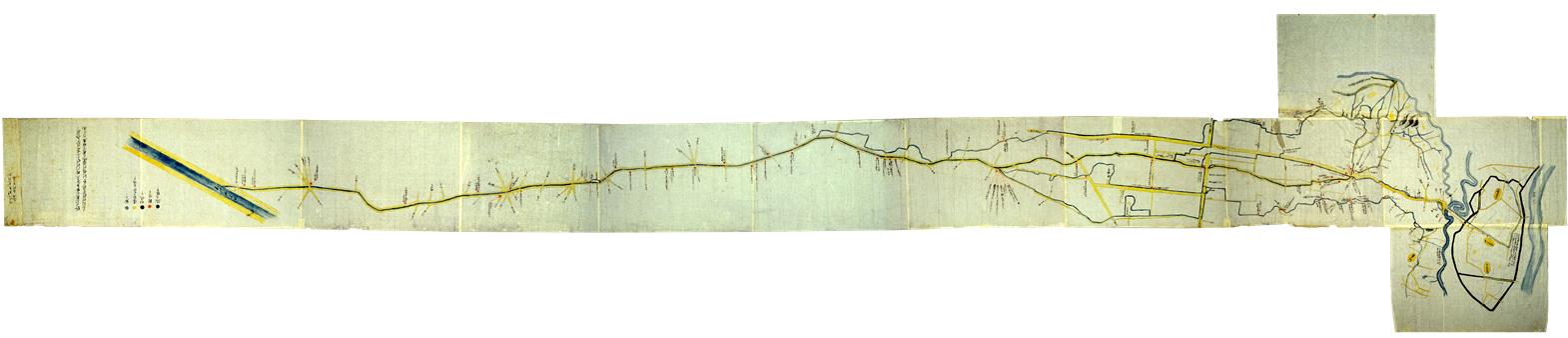本文
「睡足軒」が新座市初の国登録有形文化財(建造物)に正式登録されました
この結果を受け、8月1日付けの官報(号外第170号)、文部科学省告示第107号にて、新座市で第1号の国の登録有形文化財(建造物)となることが正式に決定されました。
登録有形文化財(建造物)とは
文化財保護法に基づき、建築後50年を経過している建造物で、次のいずれかの基準に当てはまるものが対象となります。
一 国土の歴史的景観に寄与しているもの
二 造形の規範となっているもの
三 再現することが容易でないもの
睡足軒について
概 要
(1)員数:1棟
(2)所在の場所:新座市野火止一丁目1172-1(住居表示:新座市野火止一丁目20番12号)
(3)構造・形式:木造平屋建、鉄板葺、建築面積93平方メートル
(4)年代:江戸後期/昭和13年移築
(5)登録基準:「二 造形の規範となっているもの」
主な特徴
「睡足軒」は、国指定天然記念物となっている平林寺境内林(平林寺惣門前、「新座市睡足軒の森」)内に建つ民家です。建築年代は、江戸後期と推定されています。もともと飛騨高山周辺に建てられていたものを、松永安左エ門(耳庵)が昭和13年に当地へ移築し、草庵としたと伝えられています。
松永安左エ門は、日本近代を代表する実業家の一人で、電気事業経営に尽力し、「電力の鬼」とも呼ばれた人物です。柳瀬村(現所沢市)に黄林閣(国重要文化財)を中心とする柳瀬山荘を築いたことでも知られています。茶人としても著名で、睡足軒に親しい友人を招き、「田舎家の茶」を楽しんだと言われています。
構造形式は、木造平屋建、鉄板葺で、内部は梁間一杯のイロリノマの東西に2室ずつ配置しています。木太い軸部構成や、チョウナ梁の架構、両妻への股柱の採用などに、飛騨地方の民家の特色が表れています。造作の意匠には、安左エ門による移築時の嗜好が反映されています。
このように、睡足軒は、飛騨地方の古民家の特徴に加え、昭和初期の民家活用の嗜好がよく示されていることから、「造形の規範となっているもの」に該当するとして、登録されることになりました。
なお、睡足軒とその園庭は、平成14年に平林寺から新座市へ貸与されており、体験学習や日本伝統文化の活用の場として利用されています。
見学について
通常は貸し施設のため、イベント開催時を除き、建物に入っての見学は原則できません。
施設利用がないときは、外から室内を覗いていただく形での見学となります。ご了承ください。
イベントについては、このホームページで随時お知らせいたします。
また、睡足軒の森園庭は、開園時に入場無料で自由に散策していただけます。ぜひ足をお運びください。