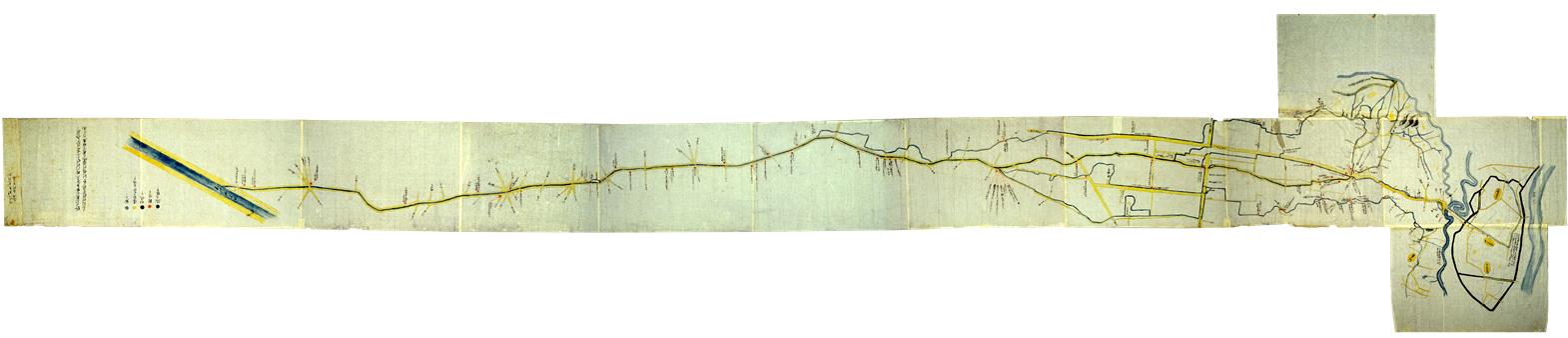本文
埋蔵文化財の手続きについて
埋蔵文化財の手続き
埋蔵文化財は文化財保護法をはじめとした法体系によって保護されており、土木工事等をする場合は、法的な手続が必要です。
埋蔵文化財は貴重な国民共有の財産であり、掘削等によって壊すことなく、保存されることが望まれます。工事の方法を工夫したり、場所をほんの少しずらしたりするだけで、発掘調査をせずに遺跡を現状のまま保存できることもあり、工事の予定や開発事業全体への影響を少なくできる場合もあります。
1.土木工事や建築行為等を行いたいとき
「家やマンションを建てたい」「店舗や工場を建てたい」「宅地を造成したい」「整地して駐車場を造りたい」など、土木工事や建築行為を行う際に、その事業地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(あらかじめ土地に埋蔵されている文化財(遺跡)の存在が知られており、市町村または県教育委員会が公開している地図と台帳に登録されている土地)になっていると、文化財保護法に定められた手続きや文化財の保護措置が必要になります。
土木工事や建築行為等を行う前には、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地になっていないか確認をしてください。にいざマップの「文化財・史跡」のページでも範囲を確認することができますが、詳細な周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲や調査履歴については、お問い合わせください。
確認後は、以下の説明をお読みの上、必要な手続きをしてください。
フローチャート (別ウィンドウ・PDFファイル・250KB)
2.事業地内に「周知の埋蔵文化財包蔵地がある」場合
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行おうとする場合、民間事業者は文化財保護法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出について」を、国・県・市町村等は同法第94条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の通知について」を提出することになっています。提出の時期は、民間事業者は行為着手の60日前までに市町村教育委員会に届け出なければならないことになっています。
届出・通知の様式は、埼玉県教育委員会文化財・博物館課史跡・埋蔵文化財担当のホームページでダウンロードできます。
- (93条・94条)埋蔵文化財発掘の届出・通知について(埼玉県ホームページへのリンク)
- 【記入例】埋蔵文化財発掘の届出・通知について(埼玉県ホームページへのリンク)
併せて、埋蔵文化財の所在の有無を確認するための試掘調査依頼書等を提出してください。
また、「埋蔵文化財発掘の届出・通知について」や「試掘調査依頼書等」には、事業地の場所を示す地図や、配置図・平面図・矩計図等の事業内容を示す図面を添付する必要がありますので、下記のページも参照してください。
なお、事業予定地が埼玉県選定重要遺跡である市場坂遺跡(新座市遺跡番号009遺跡)または嵯峨山遺跡(新座市遺跡番号015遺跡)に該当する場合は、さらに下記の書類も併せて提出する必要があります。
3.試掘調査・確認調査
「試掘調査依頼書」に基づき、市教育委員会はその工事が予定される場所を試し掘りします。これを試掘調査または確認調査と言い、実際に地下に埋蔵文化財がどの程度存在しているか、深さはどの程度かを調べます。
この調査はすべての行政指導のもとになる非常に重要な調査です。埋蔵文化財は、周知の埋蔵文化財包蔵地の全体にあるとは限らず、偏在していることもあります。一方、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲の外まで、未確認の埋蔵文化財が所在していることもあります。原則として、周知の埋蔵文化財包蔵地内で行われる工事等の前には試掘調査を行い、埋蔵文化財の位置や量などを把握しておく必要があります。
埋蔵文化財取扱手順 (別ウィンドウ・PDFファイル・224KB)
4 工事計画と埋蔵文化財の取扱いについて調整・保存協議
試掘調査の結果、埋蔵文化財の所在が確認されると、事業主には埋蔵文化財を保護する義務が生じるため、市教育委員会との間で、工事の計画と埋蔵文化財の保存方法について協議することになります(保存協議)。
まずは、埋蔵文化財を現状のまま保存するため、埋蔵文化財が所在する場所での工事を避ける方法を検討します。例えば、建物の位置を変える配置の見直しや、盛土によって埋蔵文化財に工事が及ばないようにする方法があります。現状保存(盛土保存)が可能となった場合は、発掘調査をする必要はありません。
発掘調査は、遺跡を破壊しながら記録を残す1回かぎりの行為であるため、発掘調査を避けた現状保存が優先されています。しかし、協議の結果、工事の実施によって埋蔵文化財の破壊が避けられない場合、事業主は工事前に記録保存のための発掘調査を行わなければなりません。
5 埋蔵文化財の取扱いの決定と指示・勧告
事業者と市教育委員会との協議の結果をふまえ、埋蔵文化財の届出(通知)に対して、県教育委員会から行政指導や勧告が通知されます。
(1)「慎重工事」→ 工事に着手できます
試掘・確認調査の結果、事業地に埋蔵文化財がないと考えられる結果が得られた場合に限って、予定通り工事着工を進めていただきます。ただし、工事中に埋蔵文化財が発見された場合には、すぐに工事を中止し、市教育委員会にお知らせいただく必要があります。
(2)「工事立会」→ 市教育委員会立会のもと、工事に着手できます
試掘・確認調査の結果、事業地に埋蔵文化財の所在が確認された場合でも、工事計画の変更等によって埋蔵文化財が破壊されないと確認された場合、市教育委員会の埋蔵文化財担当職員の立会のもと、工事が可能となります。届出(通知)どおりの工事が行われなかったり、重要な埋蔵文化財が出土したり、一部が破壊されたりする場合には、その場で工事を中断し、測量や写真撮影、発掘調査を行う場合もあります。
また、電柱設置のための掘削のように、事業地が狭く試掘・確認調査や発掘調査ができない場合、調査が安全に実施できない場合等でも、担当職員による立会とする場合があります。
(3)「発掘調査」
試掘・確認調査の結果、事業地に埋蔵文化財の所在が確認され、その取扱いについての協議の結果、計画や設計の変更ができなかったり、計画を変更しても埋蔵文化財を破壊したりすることが避けられない場合には、記録保存のための発掘調査を行います。この場合の発掘調査とは、現地での発掘作業から、出土した遺物や遺構の図面や写真記録類の整理作業を行い「発掘調査報告書」を作成・刊行するまでのことを指します。
発掘調査を実施するのは、埋蔵文化財の保護義務のある事業主です。しかし、通常、事業主は専門的な発掘調査ができないため、市教育委員会が発掘調査の依頼を受けて実施します。その費用については、事業主に協力を求めます。ただし、自己専用住宅や個人の農地整備などは、国・県・市町村による補助対象になります。発掘調査で得た記録を保存し、公開・活用することで、国民共有の財産である埋蔵文化財を保護したことになります。
※ 試掘・確認調査を実施できない場合でも、重要な埋蔵文化財があることが確実な場合は、発掘調査の指導・勧告を行う場合があります。
6 「発掘調査」が指示された場合
事業主と教育委員会で、発掘調査の方法、期間などについて詳細な打合せを行います。発掘調査は、遺跡を破壊しながら記録を残す行為であるため、一度しか実施できません。そのため、発掘調査には十分な期間と費用を準備し、正確な記録を作成することが求められています。
7 発掘作業の終了→工事の開始
発掘調査は現地での発掘作業の後、出土した遺物や図面・写真等の整理作業を行い、「発掘調査報告書」を作成・刊行した時点で終了となります。現地での発掘作業が終了すれば、工事が可能になりますが、同時に整理作業・報告書作成が引き続き行われておりますので、発掘調査の全てが終了するまでの期間、事業主には文化財保護についてご協力をお願いいたします。
周知の埋蔵文化財包蔵地の外で土器や石器などを発見したら(不時発見)
もし工事中に土器や石器等の遺物や竪穴住居等の遺構などを見つけたら、どうすればよいのでしょうか。偶然発見した土器や石器等は、掘ったり持ち帰ったりすることはできませんので、速やかに市教育委員会の埋蔵文化財担当にご連絡ください。また、地中からの出土品については、遺失物法の埋蔵物としての取扱いをしなければなりません。いわゆる「落し物」と同じ扱いですので、警察への届出等が必要になります。
わたしたちの個性と歴史・伝統・文化の礎となる埋蔵文化財の保護について、ご理解とご協力をお願いいたします。
【参考】
- 埋蔵文化財取扱手順 (別ウィンドウ・PDFファイル・224KB)
- フローチャート (別ウィンドウ・PDFファイル・250KB)
- 埋蔵文化財発掘の届出等に当たって (別ウィンドウ・PDFファイル・252KB)
- (93条・94条)埋蔵文化財発掘の届出・通知について(埼玉県ホームページへのリンク)
- 【記入例】埋蔵文化財発掘の届出・通知について(埼玉県ホームページへのリンク)
- 試掘調査依頼書・承諾書・誓約書 (別ウィンドウ・PDFファイル・151KB)
- 【記入例】試掘調査依頼書・承諾書・誓約書 (別ウィンドウ・PDFファイル・290KB)
- 文化財の所在の有無とその取扱いについて (別ウィンドウ・PDFファイル・117KB)